CYBERDYNE社のHAL®を使った息子のリハビリ体験談
今回は息子のリハビリで体験してきたことを踏まえて記事を書いていこうと思います。
今回リハビリで体験してきたのはこちら!
CYBERDYNE株式会社(サイバーダイン株式会社)が開発した装着型サイボーグ HAL®(Hybrid Assistive Limb)という商品です。
まずは息子がこちらの商品を使わせてもらうことになった経緯から書いていこうと思います。
息子は筋ジストロフィー(デュシェンヌ型、DMD)という病気を持って生まれてきました。すごく簡単に説明すると、体中の筋肉は毎日生まれて、古いものは壊れていくというサイクルがあるのですが、この病気は、ある年齢を境に、筋肉が生まれて維持されるスピードよりも壊れるほうが早くなるという現象が起きます。
そうなってくると、いろんなところの筋肉がだんだん細ってきて(最終的には心臓の筋肉も含む)、日常生活が昨日よりもしづらくなる……そんなことが起こってきます。
息子は現在小学三年生。令和5年の12月末までは、だんだん歩くのがきつくはなってきていたのですが、そのタイミングで「右足に体重を乗せると体を支えられない」と訴え、歩くことが難しくなりました。
そこからは、親が後ろから両脇を支えて何とか歩くという感じでした。学校は支援学級に通わせてもらっていますが、移動の際に毎回脇を持って歩いてトイレや移動教室へ連れて行ってもらうのは、本人にとっても学校側にとっても大変です。
そこで、学校生活では車いすを使う生活が始まりました。とりあえず楽天で簡易用の大人の車いすを購入し、無理やり理学療法士の先生に体に合うように見てもらい、クッションを挟んだり工夫しながら、車いす生活をスタートしました。
そして、優しい同じご病気を持つコミュニティのお母さまから「小学校のとき使っていた車いす、よかったら使って!」というありがたいお言葉をいただき、使わせてもらうことになりました。
歩けなくなったことと、身長が伸びてきたことでの変化
まず、歩けなくなることで起こった変化として、今まで歩くときに使っていた筋肉をより使わなくなるということがありました。
具体的には、膝を上げるときに使う筋肉、足を前に出すときに使う筋肉、足先を上げる動作、そしてその足と反対側で地面をけるときの筋肉など、歩くことで自然と使われていたであろう筋肉を使う機会がまるごとなくなったような状態になります。
そうなってくると、子どもの順応する力は高く、良くも悪くも“その筋肉を使わなくても生活できるスタイル”をすぐに確立してしまうんですね。
特にうちの息子の場合、「歩けなくなったことに対して、負けるもんか!できるだけ抗ってやる!」という強い意志があるタイプではなかったので、「歩けなくなったら、お尻でずるずる移動したらいいかな?」と自然に移行していきました。
親としても、これから進行していく病気であることをわかっている中で、「頑張って歩こう!」とあまり強く言うことはできませんでした。
しかし、これが立つためのお尻の筋肉の衰えや、成長に伴って骨が大きくなっても、筋肉や腱の柔軟性が保たれないことにつながってきます。
たとえば足の裏の筋や、前屈の検査でパンパンになる太ももの裏やふくらはぎの筋も、歩いて使っていれば自然に伸びていたはずが、伸びにくくなってきます。
結果として、息子の右足はまっすぐ伸びにくくなり、今では仰向けで寝ると床から数センチ浮いた状態が普通になってきました。
そうなると、身体が重くなるにつれて余計に足で踏ん張って立たなければいけないのに、右足が床にしっかりつけない状態ではそれが難しい。結果的に、さらに介助が必要な場面が増えてきます(特にトイレとお風呂)。
外出先でのエピソードとリハビリの必要性
特にトイレは、立てるかどうかで本当に大きく違ってきます。家でももちろんそうなんですが、たとえばある日の出来事をご紹介します。
──ごくごく最〜近のある日のことじゃった……
外出の際、息子が突然「トイレに行きたい」と言い出しました。そして私自身も「トイレ、パパもちょっとやばいかも!」というタイミングで、トイレを借りに行くことに。
いつもは車いすを車から降ろし、息子を座らせてトイレまで移動するのですが、この日は私も息子もかなり急いでいたため、車いすを出す暇もなく、息子を抱えてトイレに駆け込みました。
そして、息子を先に便座に座らせ、なんとか無事にトイレを済ませることができました。
すると……
次は私がトイレに行こうとした瞬間、息子は立てない。
「ちょっと待ってね、パパもちょっとトイレに……」
……どこで待つねん!(笑)by パパ心の声
まぁ、立てなくなるとそんなこともあるんですよ、という実話でした(笑)。
「パパがどうやってその場をしのいだのか気になる方は、下のお問い合わせフォームからどうぞ」(笑)
……とまあ、冗談はさておき、リアルに身体を使わなくなるということは、
① 筋肉がやせ細るスピードが早まる
② 使わない状態で身体が固まり、柔軟性が低下する
↓
結果、しっかり身体を使っていたときに比べて「できなくなること」が早くなり、
生活場面でも、本人・介助者の負担が大きくなりやすい。
そして何より、「筋力の低下が早くなる」ように感じます。
(※私は医療従事者ではないので、これはあくまで一経験者の感想です)
ここまで長々とすみませんでした。
いかに「身体をできるだけ使う習慣」が大事か、お伝えできていれば幸いです。
次はいよいよ本編!
【サイバーダインさんのHALを体験してみた〜】
の始まり始まり〜!
HAL体験記【丸亀こどもの城クリニックにて】
今回お邪魔したのはこちら!
**【丸亀こどもの城クリニック】**さんです。(※ホームページURLは記事下に掲載予定)
これから週1回以上で通う予定なのですが、中はとてもきれいで、スタッフの方々もとてもやさしく対応してくださいました。
※リハビリ中の写真は、今回は諸事情により掲載できませんが、許可はいただいておりますので、今後載せていく予定です!
さっそくHALを体験!
HALを使う準備として、足に筋肉の電気信号を拾うための電極(心電図で使うようなパッド)を貼る必要があるため、普通のズボンからサイドスリットの入ったズボンに着替えます。
息子はペタペタと貼られても特に嫌がる様子はなく、スムーズに準備ができていました。(どちらかというと、剥がすときにちょっとくっつくようですが、それもなんとかいけそうでした)
息子の場合、右膝が完全には伸びない関係もあって、少し膝を曲げた状態でHALを装着。その状態でランニングマシンの上に、上から吊るされるような形でセッティングされ、ちょうど足が地面につく高さに調整してもらい、歩行訓練がスタートしました。
半年ぶりの「歩行」に感動
訓練が始まると、2人の理学療法士の先生がついてくれました。
1人は息子の腰のあたりで、HALの動きと息子の身体を連動させるようにサポート。
もう1人はランニングマシンの制御や、息子が嫌がらないようにYouTubeを流すなど、細かい配慮をしてくれていました。
そして、ランニングマシンが動き出すと……
なんとその動きに合わせて、息子が半年ぶりに「歩いている」ではありませんか!
その姿を見られただけでも、今日ここに来た価値は十分すぎるほど。
胸が熱くなり、込み上げてくるものがありました。
本当に素晴らしい光景でした。
HALの仕組みと、私が感じた「すごさ」
私の理解した範囲で書かせてもらいますので、誤認識などあるかもしれませんが、あくまで参考程度にご覧ください。
まず、HALのすごいところは、体の電気信号を読み取り、使用者の動きに応じて必要なサポートをしてくれることです。
息子の場合、「足を上げて」と言われると、その動作をしようと脳から電気信号が送られる機能には問題がないため、HALがそれをしっかりと拾ってくれます。最初は一番低いレベルのサポートからスタートしたのですが、それでもHALの補助機能がちゃんと反応して動いてくれました。
ただ、右足の膝の伸びが悪いため、どうしても左足に体重がかかりがちでした。そこはプロの理学療法士の先生が、時間をかけて息子の身体に合わせて細かく調整し、右足にもなるべく体重が乗るよう工夫してくれていました。
データで「見える化」される動き
そして、HALに本当に感心したのが、足や胸、足の裏などにつけたセンサーから得られる波形データです。
それはまるで心電図のように、リアルタイムで「いま自分の意志でどれくらい動かそうとしているか」を可視化できるんです。
息子の場合、立つために必要なお尻の筋肉がやはり使えていないことがわかったり、足を上げるとき・蹴り出すときの筋肉の動きの偏りが、データから読み取れました。
これらの情報をもとに、**「今使えていない筋肉を、どう使えるようにしていくか」**というリハビリの組み立てを、専門家が計画してくれるとのことでした。
優しい先生方と、無事2度目のリハビリ完了!
人見知りな息子ですが、優しい先生方の声かけに、時折笑顔も見せていて、リハビリの時間が少しずつ楽しいものになっているように感じました。
ということで、今回で2度目のHALによるリハビリは無事に終了!
……はい、実は今回が初めてではありません(笑)
実は数日前に一度、体験だけのために別日で訪れていたのです。
ただその日は電極をつけない簡易体験だったため、センサー部でとれるデータのみでの説明が中心でした。それでも、今回2回目の本格的な体験で、説明していただいた内容がより理解できるようになった気がします。
おわりに
CYBERDYNE社が開発したHALという技術には、まだまだ私たちの知らない可能性があるのではと感じさせられました。
技術と医療の力で、息子の「できること」が少しでも維持していけば、これ以上にうれしいことはありません。
【丸亀こどもの城クリニック】
▶️ クリニック公式サイト: https://marugame-childclinic.com/
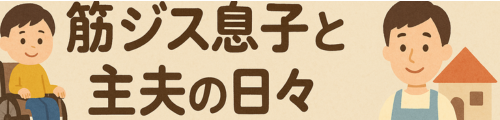

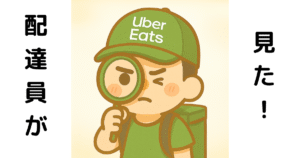

Customer Reviews
Showing 0 reviews
Thanks for submitting your comment!